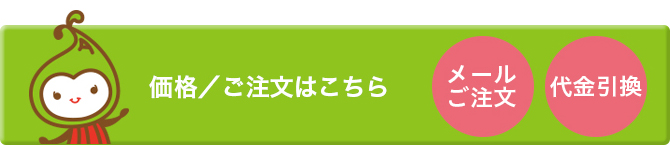- Home
- 旬のものスペシャル
旬のものスペシャル

生産者の長年培われてきた匠の技が光る一品です。
管内では一宮町と長生村を中心に栽培され、トマトと共に歴史がある「長生キュウリ」。
鮮度を重視しており、チクチクと痛いほどの「いぼ」は新鮮な証です。 また、眩いばかりの色つやとキュウリ独特の香りと歯応えが特徴です。
~効能について~
キュウリは「世界一栄養がない野菜」と言われることがありますが、実際はビタミンC、ビタミンA、ビタミンK、葉酸、ビタミンB群、食物繊維、ミネラルなどの栄養素をバランス良く含んでいます!
また、きゅうりの独自の青臭さの成分「ピラジン」は、血液をサラサラにする効果があると言われています。
血栓を予防し、脳梗塞・心筋梗塞などに効果があります。
特有成分「ククルアスコルビン酸」にはがん抑制効果があるとして注目されています。
きゅうりは90%以上が水分です。酢の物、みそ、ぬか漬けと他の調味料との相性は抜群です!
きゅうりをぬか漬けにすると、ぬか中のビタミンがしみこみ、B1の含有量はなんと8倍、カリウムとビタミンKは約3倍、ビタミンCは約1.6倍にもなります!


甘くとろっ♪
いちじくは長生管内でも、長柄、睦沢、茂原、白子など、広範囲で栽培されている品目です。
美味しいいちじくの選び方は、ふっくらと大きくて果皮に張りと弾力があり、香りのよいものを選びましょう。
いちじくには女性に嬉しい効能がたくさんあります
ポリフェノール類を多く含まれていることから細胞の酸化(老化)を防いでくれる抗酸化作用が高く、美肌に良いとされています。
食物繊維を多く含んでいることから便秘の解消だけでなく下痢止めにも効果があり、また腸内環境を整えることにも繋がり、美肌効果が期待できるでしょう。
鉄分も多く含んでおり、貧血の予防・改善にも期待できるでしょう。
タンパク質分解酵素を含んでおり、食後のデザートとして食べると胃もたれの予防や改善、糖質や脂質の消化促進にも効果を発揮することが期待できるでしょう。
生食では甘くとろっとした食感を楽しむことができます。
ドライフルーツのいちじくなら、手軽に栄養摂取ができ、また長期間の保存も可能です。
ジャムに加工して、ケーキやパンと一緒に召し上がるのも美味!

高く評価されている長生の蓮根(レンコン)
長生の蓮根は、軟らかい肉質と色白の肌合いが市場等でも高く評価されています。
蓮根は輪切りにすると穴が多数空いていることから、「先を見通す」ことに通じ縁起が良いとされています。そのため、お正月や慶事等の料理によく利用されます。
~名前の由来~
蓮根は『蓮の根』と書きますが、普段皆さんが食べる部分は、実は『茎』の部分です。
また『ハス』と呼ぶこともよくありますが、蓮根の花が咲いた後に残る花托という部分は『蜂の巣』に似ています。当初『蜂巣(ハチス)』と呼ばれていたものがやがて、現在の『ハス』と呼ばれるようになった、という説があります。
~効能について~
意外に思われる方も多いと思いますが、蓮根はビタミンCが豊富に含まれています。
本来ビタミンCは熱に弱いものですが、デンプンも多く含まれていることから、熱によって失われにくくなっています。ビタミンCは、疲労回復、かぜの予防、ガン予防、老化防止が期待できます。
蓮根に含まれる粘り成分のムチンは、胃壁を保護する効果や、たんぱく質の分解に作用します。
胃腸の働きを助け保護してくれる他、滋養強壮にも効果があるとされています。
野菜に含まれることが少ないビタミンB12を含んでいます。これは鉄分の吸収を助ける働きをします。
このほかにも造血ビタミンと呼ばれているビタミンB6も含まれているので貧血の予防が期待できます。
れんこんの切り口の変色が早いのは、ポリフェノールの一種タンニンが含まれているからです。
タンニンは消炎や止血作用があり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍に効果が期待できます。


トマト もうひとつの旬の時期
トマトといえば夏の風物詩。一般的に露地や簡易ハウス栽培のトマトが最も多く出回るのは確かに6~8月。
ですが、春本番を迎えるこれからの季節、特に暖房機を装備したハウスで栽培している当地では、秋に種をまき、冬の間に暖房しながら、大切にじっくりと
時間を費やし、育ててきたトマトの「旬」を迎えます。
トマトは、日本の梅雨~夏の高温多湿といった気候には弱く、むしろ
日照時間が長くなってきて乾燥している春の時期においしくなり、栄養価も増すともいわれています。春のトマトにも大注目!です。
リコピンパワーで体を燃焼、美容効果も!
リコピンとは、トマトの赤い色素のこと。赤色が濃いものほど多く含まれています。
リコピンは
太りにくい体作りに効果的といわれ、脂肪を蓄積する脂肪細胞の成長を抑制する作用があることが明らかになっています。また、血糖値の上昇を抑えることができるため、糖質(炭水化物)が内臓脂肪として体内に蓄積されるのを防ぐ作用などもあるといわれています。
さらに毎日の健康・美容に抱えないさまざまな栄養がバランスよく含まれています。
ミネラルも豊富なトマト。その一種、カリウムは余分な水分を体にためにくくし、
むくみを予防します。また、新陳代謝をサポートし、糖質を燃やす効果のあるビタミンB1、たんぱく質や脂肪の消化を助けるビタミンB6、シミの原因となるメラニン色素の増加を押さえ、コラーゲンの生成を促すビタミンCなども、バランスよく含まれています。
アレンジを楽しむ!トマトレシピ
トマトは、サラダなど生で食べるだけでなく、近ごろは品種によっては加熱調理に向くものも増えてきました。焼いて甘みを引き出し、肉料理の付け合せやソースにしたり、簡単トマトソースにしたり。いろんなトマト料理を楽しんでみてください!